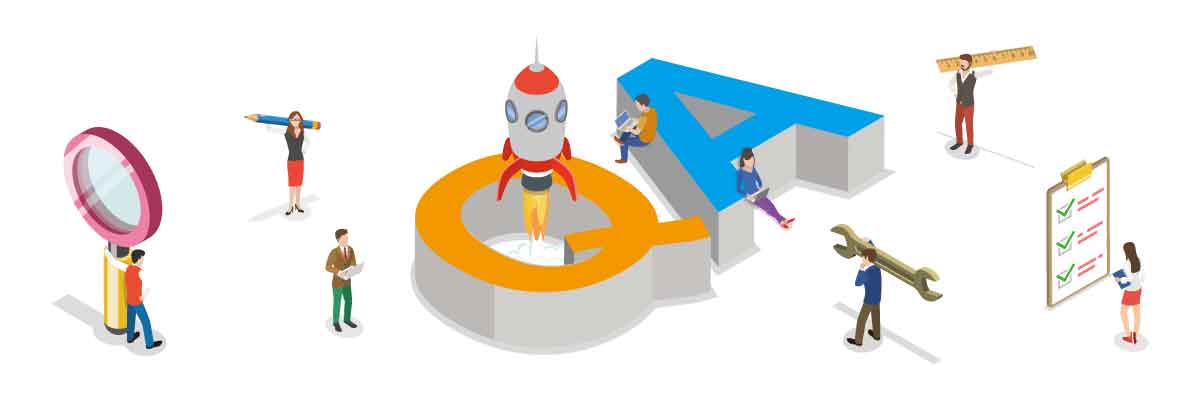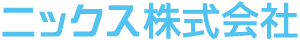皆さんこんにちは。教えてニックス!のコーナーです。
今回はプラスチックの物性についてのお話です。
以前の記事でプラスチックの種類について触れましたが、例えば同じPP(ポリプロピレン)でも品番によって物性が異なります。
私たちが樹脂の選定を行う際の指標となる「物性」についてどの様な物があるのかいくつか簡単にご紹介いたします。
■関連記事はこちら:
プラスチックの種類➀|教えて!ニックス 第7回
プラスチックの種類②|教えて!ニックス 第8回

物性の種類
メルトフローレート(略称:MFR)
樹脂を加温し、溶融した状態でどのくらい流動性があるかを示す指標です。
測定は日本産業規格(JIS-K7210)に沿って行われ、専用の試験機を用いて10分間でどのくらいの量の樹脂が流れ出たかを計測します。
単位は「g/10min」を用い、MFRが「5」だと10分間で5gの樹脂が流れ出たことを意味します。
一方MFRの低い樹脂は成形性に劣りますが、強度や耐熱性、耐薬品性等が良好な樹脂が多い傾向にあります。
曲げ弾性率
曲げ方向の力に対してどれだけ変形しにくいか(剛性があるか)を示す指標です。
測定は日本産業規格(JIS-K7171)に沿って行われ、荷重を加えて変形させたときの荷重と変形量(たわみ)から算出します。単位は「MPa」を用い、1MPaはおよそ10kgf/㎠となります。
シャルピー衝撃強度
素材(試験片)に対しハンマーで衝撃を加えて破壊するのに必要なエネルギーを数値化し、材料の粘り強さや脆さを示す指標です。数値が大きいほど衝撃に強い素材となります。
測定は日本産業規格(JIS-K7111)に沿って行われ、単位は「kJ/㎡」や「J/m」を用います。
特に低温環境(-20℃以下)において多くの物質は衝撃に対して脆くなるため、使用用途に合わせた素材選定をする上で重要な指標となります。
HAZE(ヘーズ)
素材の透明性を表す指標であり、液体やガラス、プラスチックなどの曇り度合いを表現する際に使用されます。
素材に対して光を当て、散乱した光がどのくらいの割合だったかを表し、散乱が「0」であれば素材は透明となります。
測定は日本産業規格(JIS-K7136) に沿って行われ、単位は「%」を用います。


教えて!ニックス